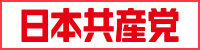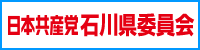日本共産党の一色眞一です。私は日本共産党を代表して質問いたします。
1.物価高騰対策について
- まず、物価高騰に対する現状認識についてお伺いします。
市民の皆さんは日々の買い物で、「また値上がりしている」、「節約も限界」と家計負担の増大に頭を抱えています。こうした現状をどのように見ておられるのか、市長の認識をお伺いします。
- 次に、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用についてお聞きします。
日本共産党加賀市委員会がおこなっている市政アンケートで、圧倒的に多いのが「物価高騰で暮らしが大変」、「貯金を取り崩している」という意見です。中にはダブルワークはおろかトリプルワークをしている人もいます。そうした苦しい生活に追い打ちをかけるように、6月からはさらなる値上げが発表されています。
今こそ「消費税廃止」を、少なくとも直ちに5%に戻せという声が多く聞かれるようになりました。
一方で、自治体独自の対策が求められているのではないでしょうか。
「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の交付金を利用したり、予算配分を見直すなどして、市民生活の支援に早急に取り組むべきと考えますが、当局の所見をお伺いします。
2.防災備蓄品について
⑴まず、防災備蓄品保管場所についてです。
5月に行った議会報告会「議会おでかけトーク」で、住民からは「加賀市の防災備蓄品が、どこに、どれだけあるのか私たちは知らないので、周知徹底してほしい」、「各地区会館に、発電機や常夜灯、毛布や防寒具、食料・水は常備してほしい」という要望が多くありました。これらの要望に対する当局の所見をお聞きします。
(2)次に、防災備蓄品保管量についてお聞きします。
市民グループが、内閣府政策統括官(防災担当)の資料を基に、人口が近い能美市を選び、対比したものを発表しています。
それによれば、簡易トイレは加賀市56台に対して能美市は215台、仮設トイレは加賀市0に対して能美市は27、携帯トイレは加賀市0に対して能美市は35,900回分、生理用品は加賀市0に対して能美市24,696枚、トイレットペーパーは加賀市0に対して能美市1,716個、パーティションは加賀市434枚に対して能美市は708枚です。
これまで、当局からは防災備蓄品については、流通備蓄により確保を図っているとの説明を受けていますが、昨年の能登半島地震で思い知らされたように、大規模災害時の物資の不足や、輸送経路の通行止め、協定先が被災した場合などの課題があり、今の状況では不安はぬぐえません。
今後も従来の方針を継続するのか見直すのか否か、当局の所見をお聞きします。
3、福井平野東縁断層帯地震評価見直しについて
先日、石川県は新たな地震の被害想定を示しました。9つの断層帯による大地震を想定しており、地震によっては、令和6年能登半島地震の被災地だけでなく、金沢市などでも大きな被害が予想されるとしています。
加賀市沖合の海域から福井県内を通る「福井平野東縁断層帯主部」ではマグニチュード7.6の大地震が想定されています。
新聞報道によると、この発表について、加賀市の担当職員は、「ここまで数が増えるとは…」と驚くとあります。また、観光業界の関係者も「大変ショックな数字だが、これぐらいを想定しておくことは必要だろう」、また「改定されるであろう市の地域防災計画も基に、行政と連携しながら対応を図っていきたい」と述べています。
- 市民の安全を担保することについて
そこで、県の見直しを受けて、市としての対応を考えているとは思いますが、県の補正予算で「住宅の耐震改修促進」として1億2,500万円を計上したことも踏まえて、市民の命と暮らしを守るという姿勢を見せていただきたい。そして、市民に安心感を持たせる必要があると考えますが、当局の所見をお聞きします。
- 災害関連死を減らすことについて
次に、災害が起きた時、何よりも犠牲者を出さないことが大事ですが、同時に災害関連死を出さないためにも、「災害発生時から48時間以内に、国際基準であるスフィア基準に基づくトイレ、温かい食事、ベッドの設置」を1次避難所に自治体の責任で行う重要性が指摘されています。
このことは、2024年12月に、石破首相が国会で述べており、これを受けたガイドラインが全国の自治体に通知されています。
では、加賀市において、この基準に基づいた対策がどこまで取られているのかを示してください。
4,小・中学校のトイレについて
- 洋式トイレ1基当たりの単価について
3月定例会で洋式トイレ1基当たりに必要な費用を尋ねたところ、令和6年度に洋式化を実施した平均では1基当たり113万円との答弁でした。その後、「なぜそんなに高いのか」というご意見が私に多数寄せられましたし、私自身も知り合いの業者に聞いたところ、「どうしてそんな値段なのか」と不思議がっていました。
そこで、なぜ、この金額になるのか、根拠を示してください。
- 洋式化する対象トイレ数について
3月定例会では、児童生徒数の減少を考慮して、今ある和式トイレ全部を洋式化の対象としないと答弁しています。では、調整後の洋式化対象数はいくつですか。また、対象を全て洋式化する場合の総額を示してください。
- 完了時期について
3月定例会では、必要数をはじき出した上で、令和7年度中に100%完了させるとの答弁でしたが、完了時期はいつになるのでしょうか。その見通しを示してください
5 国旗掲揚調査について
今年2月に、行政まちづくり課から各地区区長会長宛てに、「国旗(日の丸)の無料配布等に関する市民の意向調査へのご協力について」の依頼があったことが判明しました。内容は、町内で祝祭日に国旗を掲げている世帯の割合などを尋ねるものでした。
このことに対して、「加賀九条の会」が行政まちづくり課に質問しています。
当局から回答がありましたが、関係者によると、「質問にまともに答えていない、はぐらかした回答だった」とのことでした。
調査を依頼されたある区長会長は「こんなこと市はかまうな。ほっといてくれ」と語っていたそうです。
そもそも、市民に国旗を掲揚するかしないかの意向調査を、行政が税金を使って行うこと自体が違法ではないでしょうか。憲法第13条や第19条との整合性は取れているのか甚だ疑問です。今回のことは市民の内心の自由を行政によって侵される恐れがあります。
新聞報道によると、東京大学法学部の石川健治教授は、「国旗を掲げない人は社会から締め出されるのではという気持ちになりかねない。これは実際に日本で起きてきたこと」と指摘している。「この反省から、憲法には私たちの自由を守るための機能が内蔵されている。一人一人が憲法を理解することが自由を守ることにつながると」強調しています。
今回の意向調査についての専門家の見解をどのように受け止めているのか、当局の所見をお聞きします
先日、その調査結果が示されましたが、国旗掲揚については否定的な意思を示すデータが示されました。
そもそも、なぜ国旗掲揚が少なくなったのか。これは加賀市だけでなく、日本全国共通しています。日本人なら国旗を揚げるのが当たり前とする考え方が時代に合わなくなったとみるのが自然です。で、それだと困るからと、国旗国歌法まで制定して国旗を揚げさせようとしたのです。しかし、ここでも内心の自由を侵すべからずと但し書きを加えざるを得なかったし、法制化によってかえって国民の反発を招いてしまいました。
国旗を揚げるのは日本人のアイデンティティだの、誇りだなどと言う考えを、行政によって広めようとするのは誤りです。これは内心の自由を侵す危険な動きで、異様な同調圧力を感じます。
6,未来型商業エリアについて
- 取り決めについて
この事業は、「2025年3月末までに地権者全員の同意ない時は白紙とする」と言う取り決めがあったと聞いていますが、それは事実ですか。
それが事実ならこの事業は白紙になりますが、そうならないのはなぜですか。当初の取り決めを変更したということであれば、なぜ自ら決めたルールを無視してまでこの事業を進めるのですか?これでは到底市民の理解は得られないと思います。当局の所見をお聞きします。
*これまで加賀市は、この事業は民間のことであり、このことについては関与しないとの答弁でした。それならばお聞きします。
民間の問題だからと言いながらも、加賀市は農業振興地域の除外申請に動いたり、周辺道路の交通量調査や新たな道路建設に予算をつけたりしていることを何と説明しますか。明らかに矛盾しませんか。
民間のことと言うのなら口も手も出すなと言いたいです。そんなご都合主義で進める事業は到底市民の理解は得られないでしょう。
市民の間でも当初に比べて、今ではお荷物になるからいらないという声に変ってきています。そのことは私たちが取り組んでいるアンケートにも明確に表れています。
あらためて、市民不在の事業を断念することを強く求めます。
- 米不足について
私は、3月定例会でも「これ以上農地を減らすな」と求めましたが、当局は全く聞く耳を持ちませんでした。しかしほどなくして、深刻な米不足が起こり、改めて全国的に「減反ではなく、増産を」という流れになっています。米不足の原因は長年減反を押し付けてきた自民党政権にありますが、それに右ならえと言わんばかりに加賀市も相当な優良農地を潰そうとしています。
未来型商業エリア対象地は、農業振興地域であり、別名優良農地といわれており、安定的に米を供給する役割があります。この事業計画を撤回して農業振興地域を活かすことで、米不足を解消する一助となります。
食を預かる行政として、この対象地を転用することによる影響について想定はしているのでしょうか。その結果によっては、事業の中止を検討すべきではないかと考えますが、当局の所見をお聞きします。
以上で私の質問は終わります。
市当局からの答弁は こちら(PDF)